



立野純三(たての・じゅんぞう)
株式会社ユニオン代表取締役社長
1947年生まれ。1970年 甲南大学法学部卒業。1970年 青木建設入社、
1973年(株)ユニオン入社。1990年同社代表取締役社長。その他公職として、
公益財団法人ユニオン造形文化財団 理事長、公益財団法人 大阪産業局理事長、
大阪商工会議所 副会頭等を務める。
南條史生(なんじょう・ふみお)
1949年生まれ。日本の美術評論家、キュレーター、森美術館特別顧問。
慶應義塾大学経済学部、文学部哲学科美学美術史学専攻卒業し、
国際交流基金勤務、ICA ナゴヤ・ディレクター、ナンジョウアンドアソシエイツ
(現:エヌ・アンド・エー株式会社)を経て、2006年11月同館長に就任。
各種財団・基金等の選考委員、審査委員、等を歴任し、現在も芸術・アート業界を牽引する。
12
立野
アートというものは、どれだけいいものであっても市場に出回らないと認められませんよね。
南條
最近面白い映画を観ましてね。ナサニエル・カーン監督の『アートのお値段』っていうタイトルです。英題が『THE PRICE OF EVERYTHING』。なぜアートはあんなに高いのかっていう疑問は多くの方が感じていると思いますが、そういった疑問をもとにしてつくられたドキュメンタリー映画です。
立野
ほう。興味があります。
南條
様々な人にインタビューをしているのですが、すべて実在する人物に取材をするわけです。ジェフ・クーンズというアメリカの美術家や有名なオークショニア、ギャラリスト、コレクターなどが出演してインタビューに応えています。
立野
先生はその映画を見ていかがでしたか?
南條
一言では言い表せませんね。きっと見る人によってまったく違う感想が生まれるでしょう。
立野
ほう。
南條
ギャラリストから見ればアートは商品ですし、学者が見ると研究対象になる。そしてアーティストが見ると商売でもあるけれども、自分の生き様そのものであるという。だから結論はないのですが、「値段なんかどうでもいいんだ」っていうアーティストも多いようです。
立野
南條先生は専門家ですから様々な視点から見ておられるでしょうね。アートに関して素人ですから詳しいことは分かりませんが、私は色んなアーティストのカレンダーをもう30年近く集めています。最近は土佐尚子さんの作品を飾っていたら好評で。感覚で「この人の作品は面白いな」と思って選ばしてもらうのですがね。なのでアートは好きなのですが、例えばピカソの絵になぜあんな価値があるのかというのは実はわからなかったりします。
南條
それは単に理学的な考察ではなくて、ピカソは多作だったおかげでみんなが知っているわけですよ。みんなピカソは変な絵を描く人だということは知っていたし、その値段が高いことも知っている。経済的に見ると高いから価値があるといえます。例えば、ダイヤモンドは役に立たないけれど、みんなが高いっていうことを知っているから、身につけていると社会的地位を表現できたりもします。これとアートは少し似ているところがあって。ピカソが壁にかかっていればみんなが「ピカソですね」となる。若いアーティスト、現代アートだったら誰も知りませんから評価されにくいということはあるでしょうね。

立野
そういった絵の価値というのは画商がつくりだしていくのですか?
南條
単純に画商がつくっているわけではないと思いますね。とても複雑なメカニズムで、多分完全にコントロールすることはできないのではないかなと思います。私がよく学生に言っているのは「価値と価格は別物」ということ。
立野
ほう。
南條
ここでいう「価値」というのは何かというと歴史的な意義や初の試みであったとか様々なことが考えられます。だけれども、「価格」というのはマーケット上でいくらの価値で売れるかという極めて単純なこと。通常、このふたつは乖離しているはずなんです。
立野
先生はかつて森美術館の館長をされていて、さまざまな取り組みをされてこられましたよね。そういった展覧会のアイデアはどこから生まれているのでしょうか?
南條
美術業界に長くいたのですが、美術業界の中だけで物事を考えていると一種の自家中毒になるんです。つまり、美術っていうものが崇高であると思い続けて、美術だけの価値判断でつい物事を考えてしまう。しかし、美術というものは本来、社会の中に存在するもの。社会の一員であるし、作品の価値というのは長い時間の流れの中で決まっていくものだと思うので、自分の身をさまざまなところに置いてアートに触れるべきじゃないかと思ったんです。
立野
なるほど。
南條
先日開催された「未来と芸術」という展覧会は、先進的なテクノロジーが組み込まれていました。サイエンス・テクノロジー系は、我々が生きている周りの現実というものをどう解釈して、どういう構造になっているか、それを理論的に研究することがミッションなんです。一方で、アートはそれを直感的に表現している。これらは、プロセスは違えど、求めているものは同じで、両方クリエイティブです。これからの未来がどうなっていくかということを直感的に表現している人と、科学的に周知してくれる人、これらが混在しているものを今回展示しました。

立野
まるで万博のテーマになり得るようなことを、先取りして行っておられるんですね。今はAIなど色んな技術が発展してきていますが、絵画などは人間しかできないものなのだと今はより強く感じますよ。
南條
そこに関して面白い話があります。AIに関わっている有名な東大の教授と話していたのですが、彼曰く、ゴッホのような絵ならいくらでもAIにつくらせることができると言うのです。これはどういうことかというと、ゴッホの絵をたくさん覚えさせれば似たような絵ができると。私が考えるゴッホの凄さは、それまでアカデミックな印象はなかったのに突然、原色の平面的な塗り方で描かれた絵を出してきたところにあります。飛躍的な変化があったのですよ。
立野
しかし、コンピューターにそのような表現ができるようには思えません。
南條
そうですよね。飛躍的な変化を含め、それをコンピューターができるかどうかを問いました。そうすると、「バグがあれば変なものをつくりだすことはできる」と言うのです。バグによって突然ピカソのような絵を描くこともあるかもしれない、と。
立野
ほう。
南條
ところが、もし仮にそれをAIがやってのけたときに、「これはアートだ」という判断を一体だれがするのかという問題が出てきます。それは人間にしかできないと、私は思うわけです。その一連の話を聞いた別の人が、「ちょっと待て。そのAIがつくった変なものを、他のAIが高く評価したらどうなるのか」と言いましてね(笑)。

立野
(笑)。もしその絵をAIが描いたということが分からなかったら、人間は評価するのではないかと思いますね。
南條
そうですね。実際にAIが書いた初の絵ということで作品が発表されていましたよ。
立野
そうなのですか!
南條
初めての絵というか、AIが描いた絵を初めてオークションに出品したというのが正しい表現です。アートというものは色んな物語をつくりだすんですよ。AIがつくった最初のオークション作品っていうのは、「オークションに出品された初めてのAI作品」っていう物語に価値があるのです。
立野
私たちもカタログをつくる際に、ものづくりの物語を書くことによって評価されたりもします。だから背景は必要なのだと感じますね。
南條
だから私は物語を売る時代だと思っています。私の知り合いがパリで小さなお店をつくったんです。もともと彼はデザイナーなのですが、お店に立つときに何をしているのかを訊ねたら、日本には「包む」という伝統があると。のしとかね。それをずっと勉強していたから、その包む技術をフランスに持ち込んで、サービスをするというのです。フランスは店舗でのラッピングのようなサービスがないから、彼のお店に持ってきてくれたらきれいに包んで渡すサービスをしているようです。私は、そのサービスはフランスでは受けないと言ったのですがね(笑)。
立野
実際どうなんでしょう。成功されているんですか?
南條
彼がパリに出店して1年目の時、実際に訪れました。店内は総檜で床の間があって花が活けられていて。そこのカウンターで抹茶を出してくれたんです。彼は着物を着てお店に立っている。しかし、私の他にお客さんはいなくて、彼と30分ほど話して帰りました。2年目もお店に行きました。でもお客さんはいない。
立野
確かにフランスの方はそういったサービスにお金を使わないかもしれませんね(笑)。
南條
3年目に訪れてもまだお店は営業している。そこで、彼にどうやって切り盛りしているのかを聞いたんです。そうしたら、こういった珍しいお店をパリのど真ん中に構えることによって、ルイ・ヴィトンやエルメスが視察に来たらしいんです。そこからつながりができて、それらのブランドのコンサルをしているというんです。

立野
ほう。そうですか。
南條
今は20社と付き合いがあるそうです。
立野
20社も!それはすごい。
南條
そのお店は何も売っていないんですよ。ショールームがあるのですが、そこから物語を感じることができる。それを聞いて企画者が集まってくるようです。
立野
本当にすごいです。彼の根性もすごい。
南條
彼が初めに描いていたプランとは違うかもしれませんがね。結果的にうまくいった。きっとルイ・ヴィトンやエルメスは、彼のストーリーを評価したのだと思います。
立野
先生は、絵を描く人たちの才能は、持って生まれたものだとお考えですか?
南條
ある程度はそうじゃないかなと思います。
立野
努力して、大きく才能が開花するっていうことは考えにくい?
南條
もちろん努力で才能が開花する人もいると思います。例えば、フランスのアンリ・ルソー。彼は素朴派というジャンルにカテゴライズされていて、税関で働いていたことからドゥアニエ(税関吏)・ルソーと呼ばれていました。彼の描く絵は下手だったのですが、今ではヘタウマの走りともいわれています。そんな彼の作品は美術館に展示され多くの人から評価されています。
立野
それはつまり、どういうことなのでしょうか?
南條
私が思うに、逆の方向に向かって尖っていると、下手か上手いかっていう評価基準ではなくなってくるのではないかと。きっと彼の背景にあるストーリーが評価されたのでしょう。貧しい税関吏だけれども、40歳から一念発起し作品を発表し始めた。それが面白いという風になったのではないかと考えています。しかし、やっぱり本当に絵が上手い人っていうのは存在していて。
立野
天才と呼ばれるような方が?

南條
そうです。教えなくても構図のバランスがとれていたり、奥行きまでも構築してしまう。キャリアがなくても描いたら作品になるという人がいるのですよ。
立野
建築家でも、例えばレオナルド・ダ・ヴィンチも素晴らしい絵を描いていました。
南條
確かに昔の建築家は絵が非常に上手いです。今の建築はコピーというか、一辺倒のように感じます。だから絵が描けることと、設計図が書けることは別ですよね。
立野
丹下さん(丹下健三氏)も絵が達者でいらしたのですよ。
南條
安藤さん(安藤忠雄氏)も絵を描かれていますよね。
立野
そうですね。やはりアートと建築って通じるところがあるのでしょうか?
南條
恐らくありますよね。建築家が絵で表現するという意味ではル・コルビジェもそうでした。面白いのが、建築家が描く素描と、アーティストが描く素描はどこか空気が違う。また、彫刻家の素描も雰囲気が違います。ジャコメッティ(アルベルト・ジャコメッティ)のような有名な彫刻家がいくつか素描を残していますが、絵画の常識がないので、遠近とか、フォルムを細かく描くというのがなくて。むしろ印象でイメージをつかむ、立体を捉えるというのが強かったのです。
立野
やはりアートのジャンルによって物事のとらえ方は違うのですね。
立野
ところで、最近の画家で黒い丸だけを書いておられる方がいらっしゃいますが、あれが本当に芸術なのかとますます芸術を難しく感じることがあります。

南條
具体絵画ですね。
立野
そうです。具体美術にも歴史がありますから、そういったことを徹底してやってこられたから評価されるのでしょうね。
南條
そうですね。やはり、ある方向に向かって突き詰めてやってこられた人は強いですよ。ひょっとすると、ある方向に突き詰めていくと、どの道を選んでいたとしても最後に行きつく境地は同じなのかもしれません。これは日本的な考えなのかもしれませんがね。
立野
なるほど。
南條
アメリカの有名な彫刻家、ウォルター・デ・マリアが丸、三角、四角の彫刻を制作していて、直島にも飾られています。あの作品は、日本の影響を受けたんじゃないかなと考えています。
立野
そうですか。日本が影響を与えているものは多いですよね。
南條
多いですね。2018年から2019年にかけてフランスで「ジャポニスム2018」というものが開催されていましたが、あれは今の日本文化をフランスに持ち込んで、もう一度ジャポニズムを再来させようという狙いがあったと思うんです。19世紀初頭がジャパニズムのピークだったのですが、その時に浮世絵がフランスに入って来たりしました。それで、今までのグレコローマン、ギリシャローマ的な原理でつくられていた西洋の技術やデザインが突然オリエンタルな方向へシフトしたんです。だから、アールヌーヴォー、新しい芸術という意味ですが、何に対して新しいかというとギリシャローマの原理に対して新しいということなんです。
立野
なるほど。
南條
面白いことに、この変革を起こした人には共通点があるんです。例えば、ロックフェラーにしても新しい美術を支援したっていう人は同時にアジアを支援しているんです。だから今も、ニューヨークにアジアセンターなどがありますよね。あれはすべてロックフェラーがつくったんです。それと同時にロックフェラーは近代美術館をつくった。だから近代美術とアジア的な理学的原理は実はだいたい同じ人が支援しているんです。でも今はアーティストを支援する人がめっきり減ってしまいました。
立野
昔は「旦那」と呼ばれる支援者が多くいましたよね。
南條
いましたね。「旦那」は市場価格で動いている人ではありません。文化的なことを理解して支援してあげる人だった。例えば、芸者を居候させて、「タダ飯食っていていいから、面白い芸を見せてよ」と。何か利益を求めて支援するのではなくて、純粋に面白いと感じたから支援していたように思います。

立野
わかります。面白い人を支援して、それが結果的に利益になったり、街の資産になったりするんですよね。
南條
2年ほど前、文化庁が出した「リーディング・ミュージアム(先進美術館)」構想というものが批判され炎上したんですよ。これは、美術館が展示してない所蔵品を売りだしたらどうか、というものでした。でも美術品は展示していなくても意味があるのです。美術館はさまざまな資料が集積されているからこそ価値がある施設なのですよ。例えば50年後に1990年代の美術展をしようとしたときに、ちゃんと展示品があるということに価値がある。
立野
そのあたりが理解されていないと。
南條
はい。所蔵品を売れば、美術マーケットが活性化すると思ったようですが、これを実行してしまうとどうなるか。ギャラリーと競合になるのです。美術館というのはギャラリーから見れば、最終的に買ってくれる相手なんですよ。それが急にコンペティターになる。これは構造的にありえません。
立野
先日スイスのヴィトラに行ってきました。
南條
そうですか。あそこは椅子の展示がすごいですよね。
立野
はい。あれがまさに文化を守り育てている企業だなと思います。日本ではヴィトラのような場所が本当にありませんね。
南條
ここだけの話、東京国立近代美術館も現代美術とか外国の作家、外国のコレクターが集めたものを展示していますが、そんなことやってないで、中堅以上の大物日本人作家に大きな日本のプロジェクトをさせるべきですよ。未だにちゃんとしたものがありませんから。
立野
私たちはドアハンドルの製造を60年ほど前に始めたのですが、いまだに反省しているのは村野さん(村野藤吾氏)と一緒につくった作品をなぜ一つひとつ残さなかったのかと。今から作ろうとしてもできないんですよ。

南條
でも建築物には付随しているんでしょう?
立野
ええ。しかし、建物がなくなってしまったものはドアハンドルも残っていないんです。そこから、作品は収集するようになりました。
南條
トヨタも豊田市に美術館をつくっていますよね。あの時に多くのプロダクトを買い戻したらしいですよ。
立野
私たちもそうしないといけませんね。最終的に展示などできたら面白いでしょうし。
南條
ヴィトラは椅子だけであれだけの施設をつくっていますから、ドアハンドルだけの美術館もあってもいいですね。
立野
世界的に見てもありませんからね。世界のありとあらゆるハンドルを集めようと考えていますよ。
南條
特殊な世界でマーケットがないから集めるのは時間がかかりそうですね。建物ごと買わないといけないかもしれない(笑)。

立野
それは無理ですけどね(笑)。先生はいつも新たな発想で展示をされておられますが、アイデアはどのように生まれるのですか?
南條
私がいつも思っているのは、日本中、例えば東京に行けば美術館がたくさんあるという人がいるのですが、やはりニューヨークとかパリとかへ行くと、もっと多いことが分かります。しかもかなり特化したテーマで美術館を運営している。日本にはデザインの美術館もなければ建築の美術館もない。ファッションの美術館もありません。「美術館」と名乗っているものがいくつもあるだけなので、深く分野を極めて、その分野に特化した美術館を建てなければいけません。
立野
森美術館はそういった考えのもとで?
南條
森美術館はジェネラルですね。展覧会では深いテーマの中で展示しています。今は、もう少しアジアの方まで手を伸ばそうと思っているのですがなかなか手が回っていません。
立野
展示会を開催されたとき、タイミングが良かったと話されていましたが、世の中の時流を読みながらいつも展示会を開かれているのでしょうか?
南條
ジャーナリスティックな読みはあるのかもしれません。私が伊藤穣一氏と話した際に、イノベーションの関係者は未来の話をするけど、美術専門家っていつも昔の話をベースにしているよね。と、言うんです。私は、なるほど、と思って。美術関係者は美術史を勉強してきているんですよ。みんな過去を参照しようとしている。それが、もともと私はあまり好きではなかったんです。彼の発言を受けて「未来と芸術展」をやっている部分もあるかもしれません。やはり美術界も今後を見つめなければいけないのではないかと。

立野
素晴らしいですね。
南條
何が今後の美術につながってくるのかを考えることは、必要な視点だと思うのですよ。
立野
ヨーロッパの美術館を訪れると、子どもたちが寝転んで模写していたりしますよね。でも、日本ではあまり見かけません。
南條
日本は管理の意識が強いからでしょうね。そういうことをするとインクが付くんじゃないかとか、絵の具が飛ぶんじゃないかとかを心配するので禁止しているのではないかと。
立野
模写でもなんでもいいのですが、子どもの頃から感性を磨くためにそのあたりの規制は緩和してもいいのではないでしょうかね。
南條
そうですね。私の息子はフランスで育ったんですが、中学生の絵の宿題が「人権について描け」っていうのですよ。
立野
ほう。深いテーマですね。
南條
日本だったら、お母さんの絵を描いて下さいとか、景色を描いて下さいとか。
立野
目の前にあることを課題にしますね。
南條
ええ。でもフランスは人権をテーマにする。そうすると子どもたちは、人権の本を読んだり、新聞を読んだりします。新聞に白人の警察官が黒人を殴打したというような内容が書かれていたらそこを切り抜いて張り付けたりするわけです。結果的に描いたものはメッセージ性が強くて現代美術的な表現になっていくんですよ。つまり、言いたいことがあって作品をつくるとメッセージが中心となった作品が出来上がる。表現が写真を張り付けるとか、文章を書くとか、いかにも現代美術的な表現になっていくんです。そういう子どもたちは、現代美術が理解できないなんて言わないわけですよ。「これは何か言いたいことがあってこうしているのだろう」と、そういった思考回路になる。やはりそういった面の教育に関してヨーロッパは非常に上手いです。

立野
日本とかなり違いますね。
南條
日本は光景の世界にとどまっていると思いますね。
立野
やはり日本の教育は少し変えていかないといけませんね。
南條
全然だめですよ。
立野
世界に通用しません。先生がおっしゃるように発想から違うわけですから。
南條
日本は戦後、民主主義にしたけれども、ディベートをする文化は育ちませんでしたよね。それがいじめの問題につながっているし、人と違うことを大切にするという社会じゃないのですよ。
立野
みんなと違う意見を言うと淘汰されてしまう社会ですよね。出る杭を打つというか、そういう社会です。
南條
大人がそういう風にしてきたから、子どもも同じことをしてしまう。でも、アートという世界だけは人と同じものじゃダメなんです。人と違うことをしたら評価される。そういう考え方をもっと広げるべきじゃないかと思いますね。

立野
我々の世界でも、他社と同じことをしていたら商売にならない。やはり違うことをしないと認められないし、お客さんに買ってもらえません。
南條
みんながそういう意識になったときに初めて、クリエイティブな社会が生まれると思います。しかし、そういうことを教えてくれる先生が少ないのが現状です。
立野
みんなと同じだったら正しいというねぇ。そんなこと、楽しくないんですがね。
南條
数学は答えがありますが、アートは答えがない。
立野
だからこそ、美術という教育を注力すべきだと感じます。
立野
やはり現代美術を見ると理解できないものもありましたが、ずっと見ていると情熱を感じるというか、つくり手の想いが伝わってくることがあります。
南條
アートはつくり手がそれを正しいかどうかなんてわからずやっているわけですよ。商業デザインはクライアントがいるじゃないですか。クライアントがOKといえばそれでいい。しかしアートは、「不特定多数の誰かがきっと評価してくれるだろう」と思ってやっているわけですから。
立野
売れるまで誰がサポートしてあげるかですよね。埋もれていく人も多いでしょうね。
南條
いい作品をつくっていても消えていく人は多いですよ。
立野
そこがもったいないなと感じます。仕方ないのかもしれませんがね。淘汰される中でもつくり続けて評価される人もいるわけですし。
南條
どのようにして十分なレベルに達するのか。それを若い人たちは模索し続けているので、苦労しているでしょうね。
立野
そういう人たちが活躍できる場をつくっていかなければならないですね。

南條
ダメな時にへこたれないで続けられるかどうか。かっこいいからアーティストになっているのではなくて、自分を捨ててでも売り込むというか、人に見てもらう努力ができる人じゃないと僕らも評価できませんがね。
立野
やはり徹してアートをつくらないと認めてもらえない。これは変わりませんね。
南條
アートっていうのは最後まで不可解な世界です。なかなか理屈では表せない。
立野
若いアーティストの将来性を見込んで育てるようなことはありますか?
南條
う~ん。ありますが、いいと思ったからといって育つわけでもないので…(笑)
立野
(笑)。売り込んでくる人もいるわけですか。
南條
もちろんいますよ。見てくれって言ってきたり、推薦状を書いてくださいとか。私は割と受ける方なんですけどね。だけど、成長を予測するのは難しいですね。
立野
私たちが見ても何か感じる絵と何も感じない絵があるのですが、これは一体何なのでしょう?
南條
色んな理屈があるじゃないですか。こうしたから成功したとか、こうしたから有名になったとか。アートには様々なストーリーがあるのですが、でも結局は、作品が多くの人にとって魅力的でないといけない。そうすると、その基準は一体何なのだろうと。これを定義するのは難しいですね。私が若い頃、親しい友人と二人で美術手帖の天平を頼まれたんです。そのために、月に100か所くらい展覧会を見ました。

立野
はぁ~。凄いですね。
南條
その中でお互いにいいと思う作品は1つか2つなんです。その作品がよかったかを話し合うと、いいと思うのは大体一致するんです。さらに、ダメっていうのも一致する。だけど、意見が合わないのはどちらでもない中間の作品です。私たちは趣味趣向が違うのに同じものをいいと思った。ここが説明できないから、アートは難しいのです。
立野
これ!というのは同じなのですね。
南條
きっとみんなが思う、理屈抜きで感じる何かがあるんでしょうね。それは、美しいのか仕上がりがいいのか、それともメッセージが強いのか。それともそれ以外なのか。
立野
やはり何かしらメッセージがないと、いいと思えないと思うのですが。
南條
でも、「なんでこれがいいの?」って思うこともありますよね。その時はその作品に付随するストーリーがカギを握っている。こういう意味を持っているからこういう風にいい作品なんです。と、いった具合に。見ただけではわからないけど、説明を聞くとわかる。そういうことも多いと思いますね。でも、それはアートなのかって思う方もいるとは思います。
立野
先生から見て、世界に通用するような若いアーティストはおられますか?
南條
この前会った塩田千春はすごく評価の高いアーティストです。
立野
ほう。
南條
彼女の展覧会には結果的に70万人も来場された。今や、中国の美術館に4点の作品が展示されていますし、サンパウロでも活動している。世界中から引っ張りだこです。塩田千春の作品は赤い糸が張り巡らされていて、写真を撮ったときにインパクトがある。今はインスタグラムを多くの人が利用していますから、ネット上で拡散されて知ってもらえるというのが大きいのではないかなと思いますよ。
立野
SNSの影響力はすごいですよね。私たちは去年の4月、ミラノサローネで展示会をしました。田根剛さんにも参加していただいて、鋳物をつくるところを演じたのです。インスタグラムでも話題になって3万人の方に来場いただきました。

南條
ドアハンドルをつくっているところを実際に見てもらったのですか?
立野:
そうです。砂型に錫を流して見せたら面白いと好評をいただきました。
南條
演出にもこだわられたのでしょう?
立野
60年という歴史がありますから、会場に入ってくるまでに今まで制作した代表的なドアハンドルのコレクション、若しくはその型、鋳物を吹いた状態のものなどを最初に見てもらって、次に先ほど申し上げた、鋳物を実際に演じました。その次は、この先の未来を感じるような作品を見てもらう。それが面白かったという声をいただきましたね。
南條
それは、展覧会自体をデザインされたのですか?
立野
そうですね。全体のコーディネートを田根さんとしました。
南條
実は先週、彼と仕事をしましてね。
立野
あ!そうだったのですね。
南條:
弘前れんが倉庫美術館に関する仕事でしてね。あの赤煉瓦の建物は築100年が経っていまして、その改築を彼が担当して美術館と併用する予定です。
立野
少しだけ田根さんから聞いたことがあります。
南條
2年前に依頼しました。今や売れっ子ですよね。売れっ子になりすぎて私は心配していますよ(笑)。

立野
(笑)。田根さんもまだまだお若いですからね。これからも順調に成長していってくださると期待していますよ。このサローネも田根さんの力が加わってインスタグラムでも反響がありました。やはりSNSは勢いがありますね。
南條
そうですよね。だから、アートの評価基準も変わっていくのではないかと。
立野
というと?
南條
つまり、インスタグラムに写真をアップすると受けるアート。いわゆるインスタ映えするものに美学がシフトしていくのではないかと。昔は壁に掛けて飾っていましたが、今はインスタグラムに写真をアップする。この流れを危惧している美術関係者もいるんです。でも現実問題、この兆候ははっきりと出ていると思いますよ。
立野
そうでしょうねぇ。
南條
森美術館に来ている人の7割はネットの情報を見て来ています。一応、チラシを作って、広報・宣伝するのですが、実際にはネットの情報を頼りにして来館されているケースが多い。
立野
先ほど先生がおっしゃっていましたが、このように時代が変わるとアートも大きく変化しそうですね。
南條
美学は変わってきていると思いますね。芭蕉の言葉に「不易流行」っていう言葉がありますが、流行の中にも普遍があるっていう意味で理解されているじゃないですか。変わっていく美学の中にその時代の真実が宿っているとも考えられます。だから、「あんなものただの流行だ」って否定ばかりしていると時代からずれてしまう。
立野
もちろんアップデートしなければいけないこともありますが、変えてはいけないところもありますよね。美術でも基本的なことは学ばないといけないと思いますし。
南條
面白い話があるのですがね、「不易流行」っていう言葉を中国人に見せたらそういった意味には解釈できないって言うんですよ。流行は容易いものではないっていう意味にとらえられる。
立野
たしかに流行は容易く生み出せるものではないですからね。
南條
作ろうと思ったら大変ですよね。
立野
先生の仕事を見ているととても楽しんで日々働かれているように感じますよ。
南條
いやいや(笑)。美術っていうのは永遠に議論をし続けなくてはいけないし、しかも結論がない。大変ですよ。
立野
今も森美術館のお手伝いをされているのですよね?

南條
そうですね。今は外の仕事も増えて来ていて、さっき申し上げた弘前の美術館の件もそうですし。もともと、自分で作った会社があるんですよ。そこが今度、トヨタの美術館の管理をするというので、そこを手伝ったり、台湾にも美術館ができるとのことでそこの手伝いを頼まれたり。大きなプロジェクトはいくつかいただいています。台湾の美術館はレンゾ・ピアノが建築を手掛けるんですよ。
立野
レンゾ・ピアノですか。それはすごい。
南條
森美術館を手掛けた建築家がコンサルをして大体の方向性が見えてきたので、これから中身を進めていくところです。
立野
森美術館には私たちの商品を使っていただいていますよね。ありがとうございます。
南條
そうですよね。弘前の美術館も確かユニオンではなかったですか?
立野
たぶんハンドルはやらせて頂いていると思います。
南條
できた時はぜひ見に来てください。
立野
もちろん行かせていただきます。田根さんとされているなら多くの方が来館されるでしょうね。日本人も美術館が好きですから。
南條
そうですね。少し話が戻りますが、アートマーケットが日本は弱い。作品を買う人が少ないのです。ただ、美術館に行く人は多い。
立野
そうですよね。私もヨーロッパに行った際には美術館へ訪れますが、日本人をよく見かけますよ。
南條
そうですよね。だから、もうすでにシェアリングエコノミーにシフトしているのではないかと思うのですよ。自分で作品を所有しないで、公的な施設が保有し、そこへ大勢の市民が作品を見に行く構造に変わっている。
立野
欧米だと個人が作品を購入する文化が根強いですよね。だから日本人も文化を買うということに興味をもっと持ったらいいと思うんですよ。
南條
そうなんですよね。そうしないと若い作家がアートで食べていけない。今はマーケットの三分の一がロンドン、そして三分の一アメリカ、その残りが中国なんです。日本はわずか数%です。GDPを見ると日本は3位じゃないですか。絶対にこのマーケットの割合はおかしいと思います
立野
昔みたいに旦那の気分で購入する人が出てきたらいいですね。
南條
立野さんは旦那になっていただいていると思いますので、是非アートの方も(笑)。
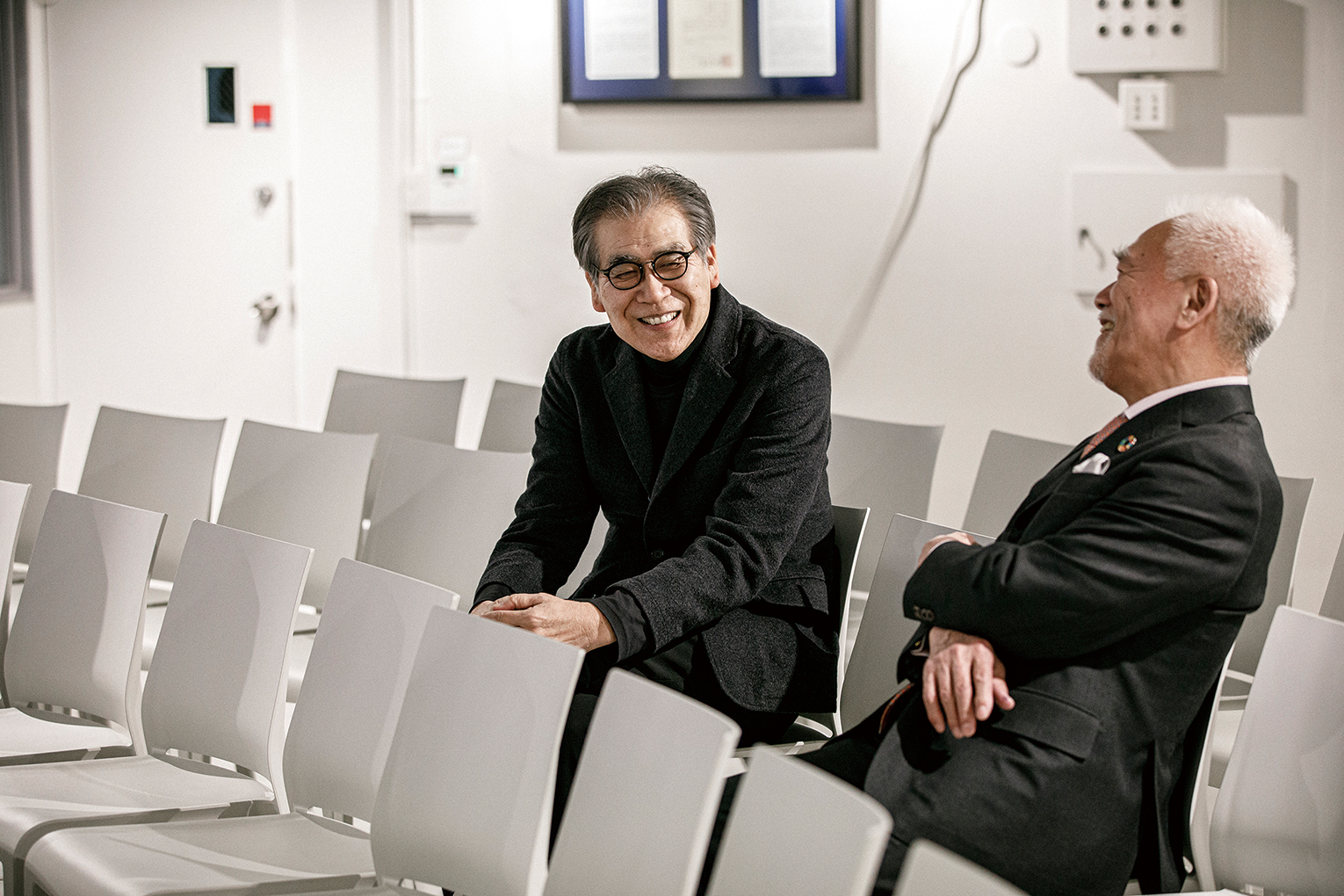
立野
(笑)。僕はカレンダーなどの作品は一応すべて買うようにしています。過去のものも残していますよ。日本の若いアーティストの方たちも海外に出ていかないと食べていけないのでしょう?
南條
そうですね。
立野
隈研吾さんはいまものすごく売れておられるじゃないですか。昔の建築家の先生は長生きされますね。日本にはたくさんの著名な建築家の先生がおられますから、しっかりと建築美術館をつくって後世に遺していってほしいです。
立野
前回、太田伸之さんと松村光さんと対談をさせていただいたのですが、ワコールがファッションの資料を大量に所有されているみたいですよ。
南條
ワコールさんの資料は世界でも五指に入ります。18世紀ごろからの西洋の服を持っておられますよ。
立野
そういうことを日本の企業がどんどんやっていかないといけませんね。
南條
ほんとうに。ワコールさんは自社の製品ではなくて、歴史的な作品を集めていますから大したものです。ファッションというものはテキスタイル、つまり布ですよね。だから保存が難しいのですよ。18世紀の布が残っているというのは稀有な例です。
立野
そうなのですね。
南條
きちんと形も残っているから非常に貴重です。一度その服をお借りしてファッションの展覧会をしました。驚くことに、19世紀の宮廷に仕えている人は腰を締めているんですよね。だから今のマネキンに着せることができないんですよ。マネキンをつくるところから始めるんです。

立野
ほう。それは面白いですね。相当細かったんでしょうね(笑)。
南條
いや~驚きました。これで生活していたんだから異常ですよ(笑)。このように展覧会を通して色々勉強させていただいています。
立野
先生は本をいくつかお書きになっていますよね?
南條
はい。『美術から都市へ―インディペンデント・キュレーター15年の軌跡』という本を鹿島出版社から出しているのですが、パブリックアートとかそういったことを中心に書いています。そのあと『疾走するアジア―現代アートの今を見る』でアジアの美術のことを語っています。三つめが『アートを生きる』。なぜ自分が現代美術にかかわるようになったのかを書きました。もう一冊書くべきだなと思いつつ、まだ進んでいません(笑)。
立野
(笑)。楽しみにしています。

南條
今後は自分の経験を若い人たちに伝えていかなければいけないっていう想いもあるんです。
立野
それは是非、若い人たちに伝えて欲しいですね。講演の回数を増やして先生の経験について話されたら多くの方が喜ぶと思いますよ。
南條
ただ、ソリューションの仕方に関しては、時代が変わって違うものになっているかなと。今は情報の流れもインターネットが主流ですし、若い人の働き方も変わってきていますから。こういった、新しい環境の中で私がやってきたことが果たしていいものなのかどうか…。
立野
先生、それは伝えていくべきだと私は思いますよ。若い人も知りたいと思っている人が多いはずですから。
(終了のお知らせ)
一同
ありがとうございました。
Planning:宮本 尚幸
Photography:宮西 範直
Writing:太洞郁哉
Web Direction : 貴嶋 凌